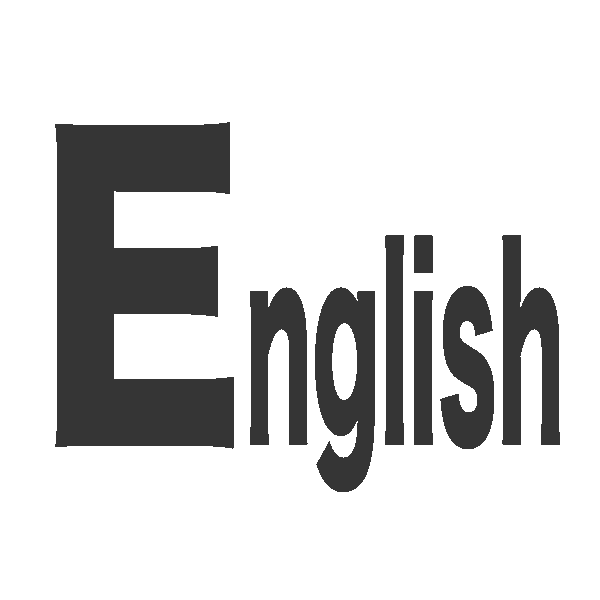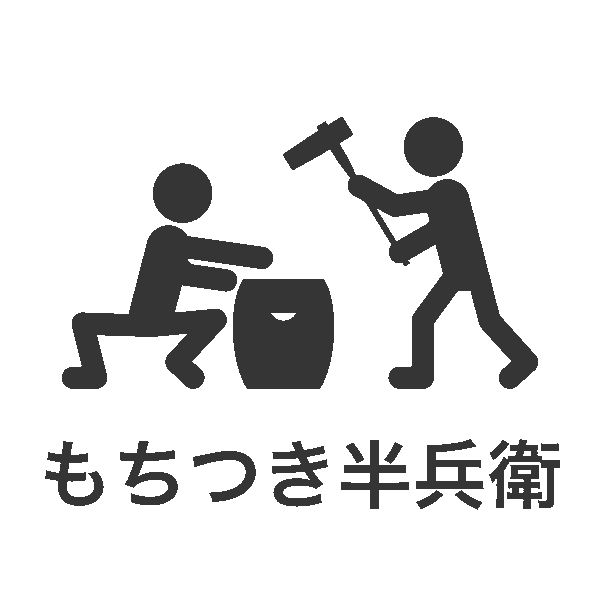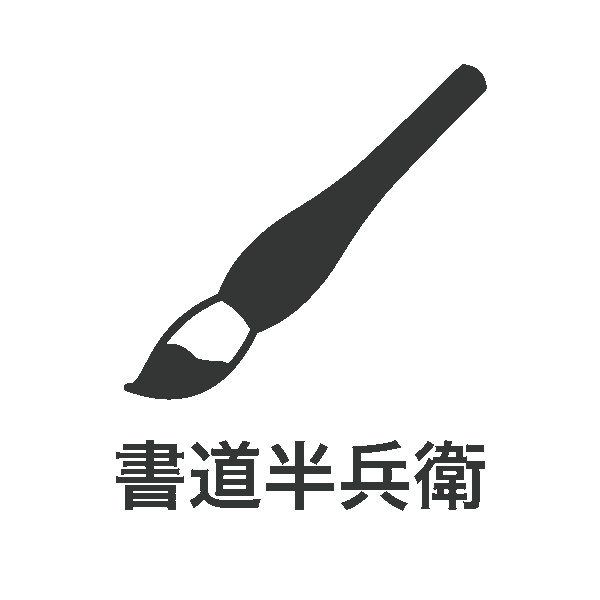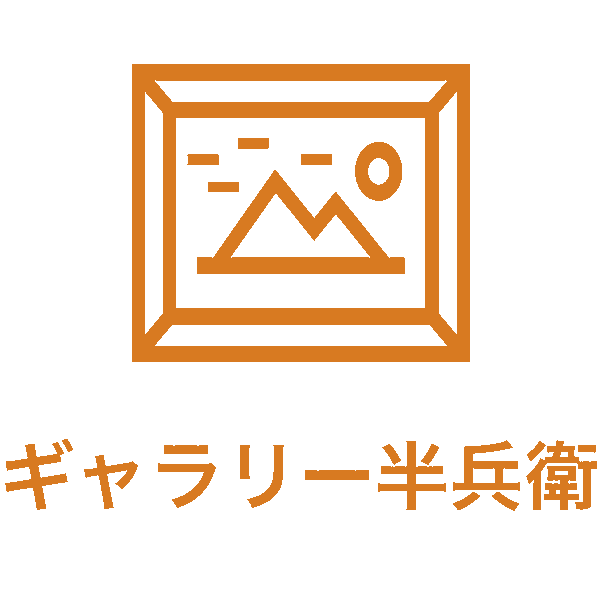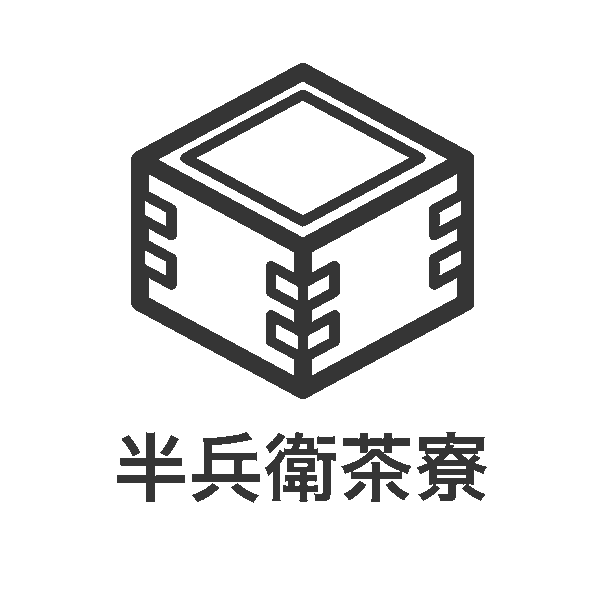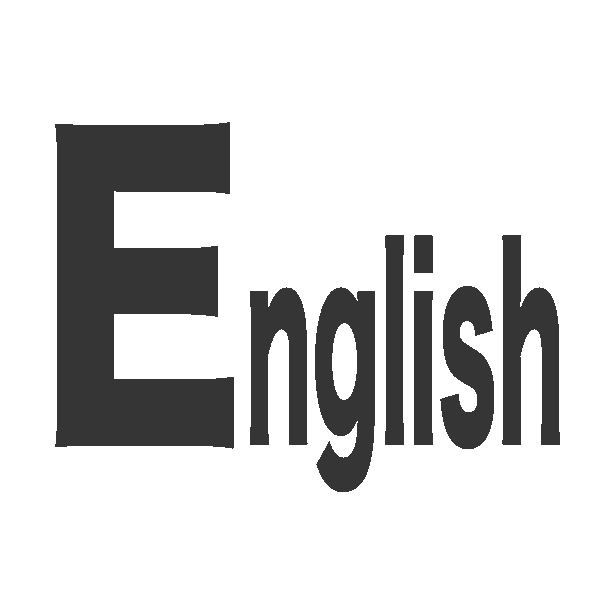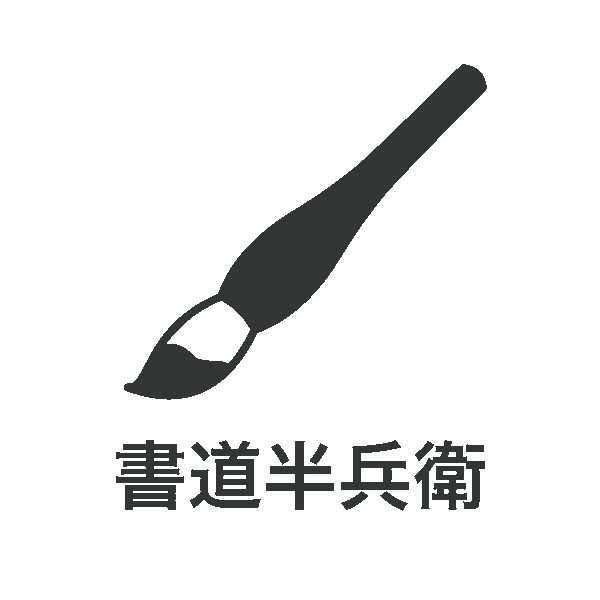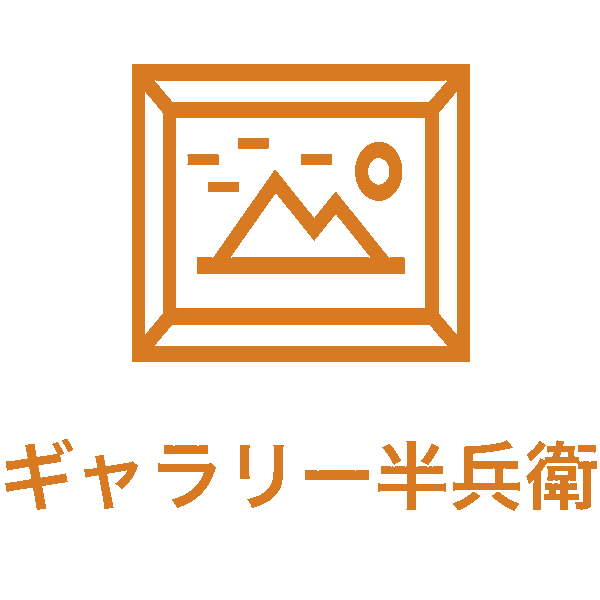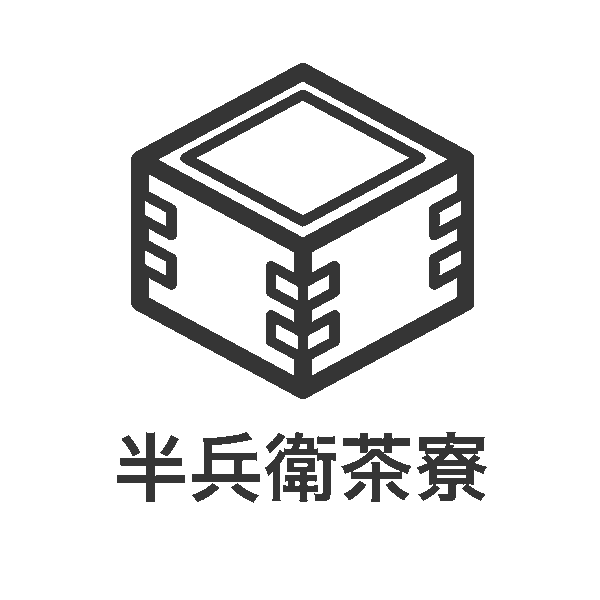茶道とは
茶道(さどう)は、日本独自に発展したお茶の文化であり、「お茶を点てていただく」という行為を通して、心を整え、人と人とのつながりを大切にする伝統芸道です。
単に抹茶を飲むことが目的ではなく、亭主(おもてなしをする人)と客が一体となり、心をこめておもてなしをし、互いにそのひとときを味わうことが茶道の本質です。
茶道は16世紀、千利休によって大成されました。
質素で簡素な美を尊ぶ「侘び寂び(わびさび)」の精神を背景に、茶室、茶碗、掛け軸、庭、香など、空間全体がひとつの芸術として調和しています。
また、茶道は「一期一会(いちごいちえ)」という考え方を大切にしています。
これは「今日この場で出会う人と体験は、一生に一度きりのかけがえのないもの」という意味で、茶道におけるおもてなしの心を象徴しています。

茶道の歴史
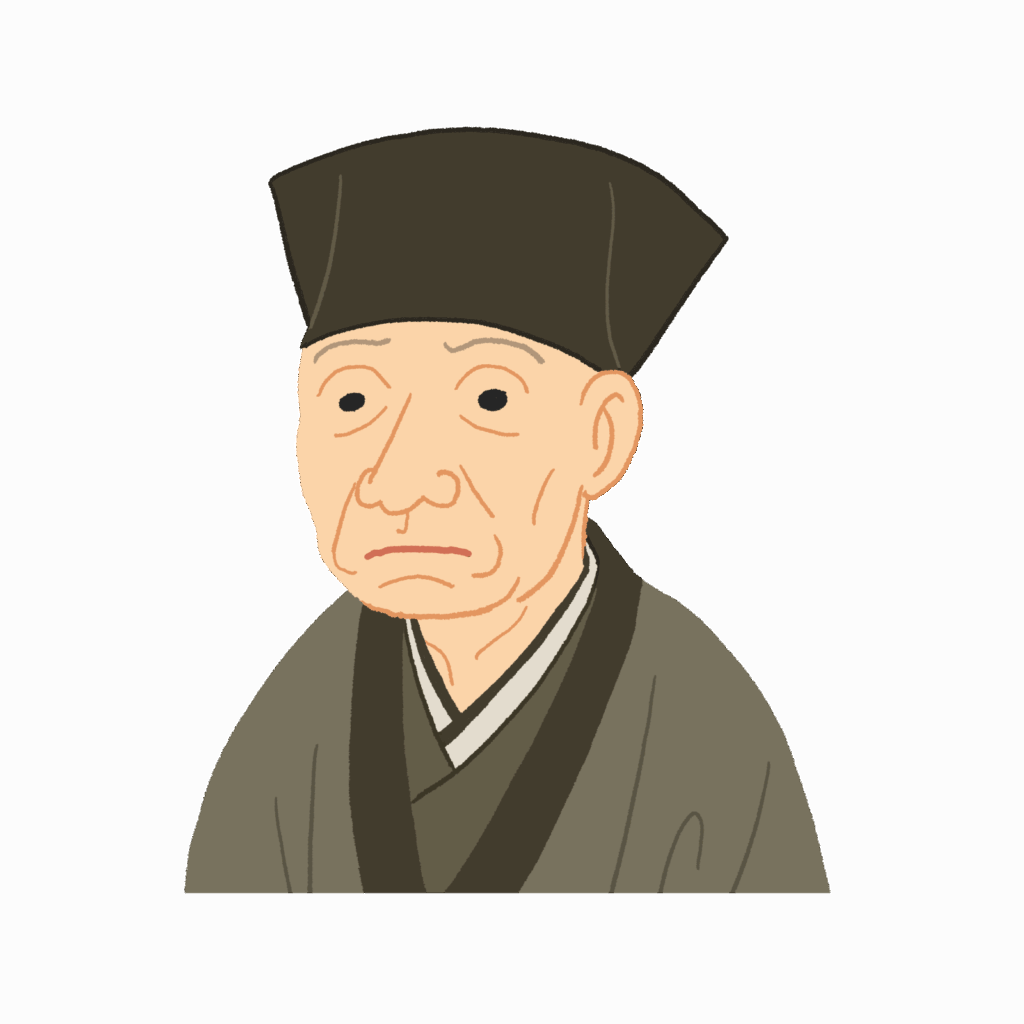
茶道は、西暦800年代に日本へ伝わった中国の喫茶文化を起源としています。
鎌倉時代(1185〜1333年)には禅僧・栄西が茶を広め、精神修養の一環として寺院で飲まれるようになりました。 室町時代(1336〜1573年)になると、茶の湯は武士や貴族の社交の場として発展し、やがて千利休(せんのりきゅう)によって「侘び寂び(わびさび)」を基盤とした精神性が大成されました。
利休の影響は現代に至るまで続き、茶道は「お茶を飲む行為」を超えて、日本の美意識や礼法を体現する文化として根付いています。
茶道具(茶碗・茶筅・茶釜など)の説明
茶道では、多くの道具が使われますが、代表的なものを紹介します。
- 茶碗: 抹茶を点て、いただく器。形や大きさ、季節に合わせた選び方があります。

- 茶筅(ちゃせん): 竹で作られた泡立て器。抹茶を点てるときに使い、きめ細やかな泡を立てます。

- 茶釜(ちゃがま): お湯を沸かすための鉄製の釜。湯気や音も茶の湯の雰囲気を演出します。

- 柄杓(ひしゃく): 茶釜から湯を汲む竹製の杓子。

- 茶杓(ちゃしゃく): 抹茶をすくう細長い竹の匙。

茶道の流れ(お点前の手順)
茶道のお点前は「お茶を点てて、お客様にお出しする」一連の作法です。基本的な流れは以下の通りです。
茶道具を清め、所定の位置に整える。
茶碗に抹茶を入れ、茶筅で湯を混ぜ、細かい泡を立てる。
お客様に丁寧に茶碗を差し出す。
客は茶碗を拝見し、感謝の言葉を添えて抹茶をいただく。
茶道具を清め、元に戻す。
茶道が大切にする精神(和敬清寂)
茶道には、大切にされている4つのキーワードがあります。
1. 和(わ)
人との調和ややさしさ
茶室では身分や国籍を問わず、すべての人が平等です。お互いを尊重し、調和の心で空間を共有することが大切です。
2. 敬(けい)
お互いを尊重する気持ち
客人、亭主(ていしゅ)、道具、季節、自然など、すべてに対して敬意をもって接します。ひとつひとつの動作や言葉に、思いやりの心が表れます。
3. 清(せい)
きれいに整えること、心の清らかさ
茶室や道具は常に清潔に保たれ、見た目の美しさも大切にされます。心の中の「清らかさ」も意識します。
4. 寂(じゃく)
静けさ、落ち着いた心
茶道は静かな環境の中で、心を落ち着かせ、自分と向き合う時間でもあります。現代の忙しい生活の中で、貴重な「心の休息」の場です。
茶道体験を通して
茶道体験では、お茶の点て方や作法を学ぶだけでなく、日本人が大切にしてきた「心のおもてなし」に触れてください。
茶道は五感を使って感じる文化です。味、香り、音、所作、そして茶室の空気そのものを楽しんでください。
慌ただしい日常と茶室で流れる時の流れの違いを感じてください。